床にマットレスを直置きして使うと段差が低くなり安全性が高まりますが、カビが生える心配もありますよね。
カビやダニは湿気を好み、繁殖するとアレルギー原となり健康被害を引き起こす場合もあります。
除湿シートがあれば、マットレスと床の間に溜まる湿気を吸い取ってくれるので簡単にカビダニの対策ができますよ。
私は引っ越しを機にベッドマットレスを床に直置きして使っていますが、特に対策をしていないためカビが心配になり、今回除湿シートの正しい使い方を調べました。
しっかり効果を発揮させるための除湿シートの選び方や使い方、カビダニの繁殖を防ぐ対策方法を解説しているので清潔で安全な寝床を作れるようになります。
除湿シートを正しく使いこまめに掃除やお手入れをすることで、マットレスの直置き生活を楽しみましょう♪
こちらの除湿シートは湿気をたっぷり吸うとセンサーが色でお知らせしてくれるので、干すタイミングが分かって便利です!
風通しの良いところに干せば吸湿力も回復するので繰り返し使えますし、マットレスの下に敷くだけで簡単に湿気対策ができますよ。
マットレスを直置きするなら除湿シートで湿気対策!

フローリングや畳にマットレスを直置きするとカビやダニの発生が心配ですが、除湿シートを敷くことで防ダニ防カビの効果がありますよ。
私は子供たちの落下が心配で、2つのマットレスを床に直置きして並べていますが、除湿シートは使っていないので、カビの発生を心配していました。
除湿シートの必要性や使い方を調べると、自分に合った除湿シートを選ぶことでお手入れが楽になり、清潔な睡眠環境を作れると分かりました!
しっかり効果を発揮させるには正しい使い方が必要なので、おすすめの商品と一緒に解説していきますね。
直置きは湿気やすい!カビダニを防ぐための除湿シート
カビやダニの発生を防ぐにはマットレスに湿気を溜めないことが大切で、湿気を吸湿するアイテムが除湿シートです!
- 寝具の湿気を吸湿するシート
- 干して乾燥させれば何度でも使える
マットレスにカビが生えたりダニが発生したりするのを防ぐ効果があり、寝具がジメっとする不快さを解消する役割もあります。

ウレタン系のマットレスは特に湿気が溜まりやすいので除湿シートが有効です!
- 寝汗が浸透して畳や床に溜まる
- マットレスの温度と畳や床の温度の差で結露ができる
人は寝ている間に想像するよりもたくさんの汗をかいていて、その寝汗が寝具やマットレスを通ることで床に湿気が溜まってしまいます。

いくら部屋を涼しくしても、子供たちは汗だくで寝ていることがあります。
冬場はマットレスは体温で暖かいですが、床の温度は冷たいため温度差で結露ができてしまう場合もあるのです。
床に溜まった湿気や結露をそのままにしておくと、マットレスにカビが生えたりダニが発生したりする心配があるので対策をしておきたいですよね。
ベッドに比べてマットレスの直置きは湿気が溜まりやすいので、除湿シートを使ったり定期的なお手入れをしたりする必要があります。

除湿シートはマットレスに必須ではないけれど、あると助かるアイテムです!
正しい使い方とお手入れで除湿シートの効果を高めよう
湿気対策で除湿シートを使っても、正しく使えないと効果を発揮できずカビやダニが発生してしまっては意味がありませんよね。
除湿シートはマットレスの下に敷き、定期的に干してシートに溜まった湿気を放湿する必要があります。
「床→除湿シート→マットレス」の順になるように除湿シートは寝具の一番下に敷き、マットレスに溜まる湿気を吸い取らせます。
- 吸湿量がMAXになったら天日干しをしてシートに溜まった湿気を放湿する
- 陰干しや室内の風通しの良いところに干すだけでも良い
吸湿量を教えてくれるセンサーが付いていない場合は、マットレスの種類や季節にもよりますが、1~2週間に1回は干しましょう。
シーツを洗うタイミングで除湿シートも干せば、一度の手間で済みますし気分的にも気持ちが良いと思いました。
定期的に乾燥させることで、シートが破れない限り半永久的に使えますが、吸湿・放湿が十分でないと感じたら買い替えをおすすめします。

洗えるタイプを選べば洗濯機や手洗いで汚れを落として、衛生的に使えます!
どんな除湿シートを使えば良いのか、続いてはマットレスの種類やお手入れに合わせた選び方を解説していきます。
適切な吸湿量で簡単お手入れ♪除湿シートの選び方
除湿シートは、自分が使っているマットレスの特徴やお手入れの頻度から必要な吸湿量を考えて商品を選ぶと良いです。
目的に合わせて除湿シートを選ぶことで、効果的に除湿したりお手入れの手間を減らしたりできますよ。
| マットレスの種類 | マットレスの特徴 | おすすめの除湿シート |
|---|---|---|
| ベッドマットレス | 分厚く重たい | 吸湿量が高いもの |
| ウレタンマットレス | 軽く手入れがしやすい | 吸湿量が低いもの |
| ファイバーマットレス | 通気性が良く湿気が溜まりにくい | 除湿シートは不要 |
私はシングルとクイーンサイズのベッドマットレスを直置きしていますが、結構な重さがあるので立てかけるのが大変で、頻繁に除湿シートを取り換えるのは手間がかかります。
ウレタンマットレスでも、手入れをなるべく減らしたい場合は吸湿量の多い物を選べは手入れの頻度を減らすことができますね。

吸湿量が多いと価格が上がりますのでお財布と相談して決めると良いです。
2000円程度で販売している除湿シートは吸湿量が少ないことが多く、ベッドマットレスに使う場合は干す頻度が高くなるので注意しましょう。
吸湿量以外で選ぶ場合は、水洗いが可能か、吸湿量を知らせるセンサーが付いているか、抗菌防臭消臭機能が付いているかなどが判断材料になります!
TEIJINの除湿シートに使われてるベルオアシス(R)という素材は、吸湿力が非常に優れていてシリカゲルの2~3倍もの吸湿力です!
マットレスの湿気だけではなく空気中の湿気も吸い取ってくれる効果があるので、寝室の湿度調整もできて爽やかな睡眠を作り出せますよ。
吸湿量が多いのでお手入れの頻度が少なくて済むのは嬉しいポイントで、防ダニ加工や抗菌防臭機能もあるので敷くだけで清潔な寝床になります。
マットレスの直置きは対策必須!カビダニを防ぐ方法

マットレスの直置きは、安全性が保てたり部屋の圧迫感を減らしたりする効果がありますが、カビやダニ発生のリスクもあり除湿シートだけだと万全とは言えません。
カビやダニは直接健康被害を引き起こす可能性もあるので、特にアレルギー体質の場合はしっかりとした対策をしましょう!
除湿シート以外に取り組めるカビやダニの発生を防ぐ対策方法や、マットレスのお手入れの仕方について解説します。
床にマットレスを直置きするメリットとデメリット
安全性を高めるためにマットレスを直置きしている場合も多いと思いますが、カビやダニの発生の可能性が上がるデメリットもあります。
- 安全性が高い
- 部屋を広く見せる
- 低コスト
直置きすることによって寝具の高さを抑えられ、圧迫感が減るために部屋が広く見えたりおしゃれに見えたりします。
私は掃除のタイミングなど定期的にマットレスの向きを変えて気分転換しますが、ベッドフレームがあったら簡単に模様替えはできなかったと思います。
ベッドフレーム代がいらないので費用を抑えられますし、その分マットレスや寝具にお金をかけられるのは嬉しいですね。

組み立ての必要がないので、引っ越も楽になりますよ♪
- 湿気、カビ、ダニの発生
- ハウスダストを吸い込みやすい
- 底冷えする
湿気はカビだけでなくダニにとっても好条件で、直置きマットレスは湿気の逃げ場がないのでダニも繁殖しやすくなってしまいます。
ダニは暖かく湿った環境を好み、特にマットレスにはエサとなるフケや剥がれ落ちた皮膚片、皮脂などがあるためダニにとっては居心地の良い場所です。

マットレスに湿気が溜まると、コイルがさびるなど耐久性にも影響が出ます。
床から近いところで寝るので、床に溜まっているホコリやハウスダストを吸い込みやすくアレルギーの原因になってしまうこともあるので注意が必要です。
直置きしていると冬場は床の冷気がマットレスから体に伝わるため、体が冷えてしまい睡眠の質を落としてしまう可能性もあります。

直置きの布団で寝ていたとき、冬場は底冷えで本当に寒かったです。
息子がダニアレルギーを持っていることもあり、個人的にカビダニの体への影響が気になったので詳しく調べました。
カビ発生ダニ繁殖は健康被害を引き起こすので要注意!
カビもダニも人によってはアレルギー症状が出たり、皮膚や呼吸器に症状が出る感染症を引き起こしたりする場合があり注意が必要です。
どちらも日常生活の中に身近に存在しているものではありますが、免疫力が落ちている場合や、小さな子供やペットは影響しやすいのでしっかり理解しましょう!
| カビの健康被害 | 症状 |
|---|---|
| カビ感染症 | ・健康な状態なら影響はないが、免疫力が落ちていると感染リスクが高まる ・皮膚や呼吸器に症状が出る |
| カビアレルギー | ・胞子を吸い込むことで症状が出る ・アレルギー性鼻炎、気管支喘息、アトピー性皮膚炎など多様な症状 |
| カビ中毒 | ・長時間カビを接種し続けると現れることもある ・肝臓障害、腎臓障害、がんなど |
カビの胞子は目に見えないので、カビが生えていることに気づかないと知らない間に吸い込んでしまうので恐ろしいです。
一度生えたカビは落とすのも手間がかかり、マットレスのように水洗いできない物だとしっかり処理できるかも不安なのでなるべく生えないようにしたいです。

個人的には、カビが生えたマットレスは処分すると思います。
| ダニの健康被害 | 症状 |
|---|---|
| 皮膚炎 | ・寝ている間に刺されることで肌にかゆみや炎症を引き起こす ・非常に強いかゆみが1週間以上続く |
| アレルギー | ・布団で繁殖したダニのフンや死骸を吸うことで引き起こされる ・アレルギー性鼻炎、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、結膜炎など |
私の息子はまだ小さいので布団で飛び跳ねで遊んでしまうことがあり、そのあとは必ずくしゃみ、鼻水、目のかゆみを訴えます。
ダニも家の中にごく普通にいる生き物ではありますが、死骸を吸いこむというのは想像したら気分が悪いですよね。

息子のためにも、しっかり対策をしたいと思いました。
カビやダニの発生は怖いという印象を持ちましたが、適切な対策や定期的なお手入れをすることで発生を防ぐことができるので安心してくださいね。
マットレスの陰干しと換気で湿気を溜めずにカビ対策
一度生えてしまったカビはなかなか取れない場合もあるので、カビが生えない対策をしておくことが大切です。
除湿シートを敷くほかにも、マットレスの置き方や寝具選びを工夫し、部屋の換気やマットレスの陰干しをすることで、湿気対策ができカビの発生を防げますよ。
マットレスの置き方や部屋の換気は簡単にできるので、すぐにでも取り組みカビ対策をしましょう!
- こまめに陰干し
- 起きたら掛け布団は畳む
- マットレスの置き方を工夫する
- 機能的な敷きパッドを選ぶ
- 部屋の換気をする
マットレスは普通に使っていても寝汗や湿気でじめじめとした環境になるので、こまめに陰干しをして湿気を取れると良いです。
| マットレスの種類 | 干す頻度 | 干し方 |
|---|---|---|
| ウレタンマットレス | 3日に1回程度 | 風通しの良いところに陰干し 熱に弱いので天日干しNG! |
| ベッドマットレス | 2週間~3週間に1回程度 | 重たい場合はマットレスの片側に本を挟んで空間を作る 扇風機で風を送ると効果的 |
掛け布団の敷きっぱなしは湿気がこもるので起きたら掛け布団は畳み、マットレスが薄い場合は立てかける習慣をつけると毎日陰干しができます♪
窓や壁の近くは結露や空気が溜まって湿気っぽくなるため、マットレスは窓と壁から10cm程度離して置き、空気の通り道を作りましょう。
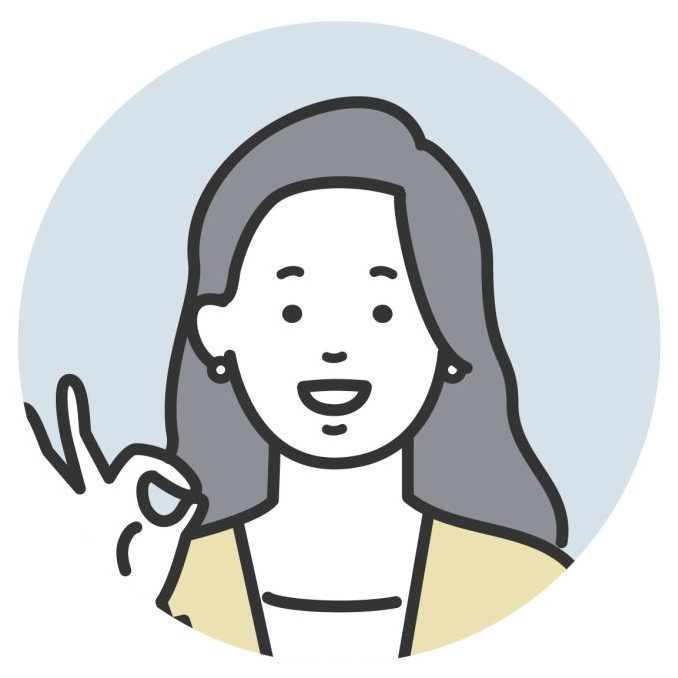
壁側にくっつけてしまいがちなので、子供が落ちない程度に離そうと思います!
どうしても床に直置きしたいわけでなければ、すのこを一枚敷けばマットレスの下にも空気を通せます。

すのことマットレスの間には除湿シートを敷きましょう。
マットレスに寝汗が浸透しないように機能的な敷きパッドやベッドパットを使うことで、湿気対策になりますし、マットレスの劣化も防げます。
冷感効果のある敷きパッドで寝汗を抑えたり、防水加工のしてあるベッドパットで寝汗の浸透を防いだりしましょう。
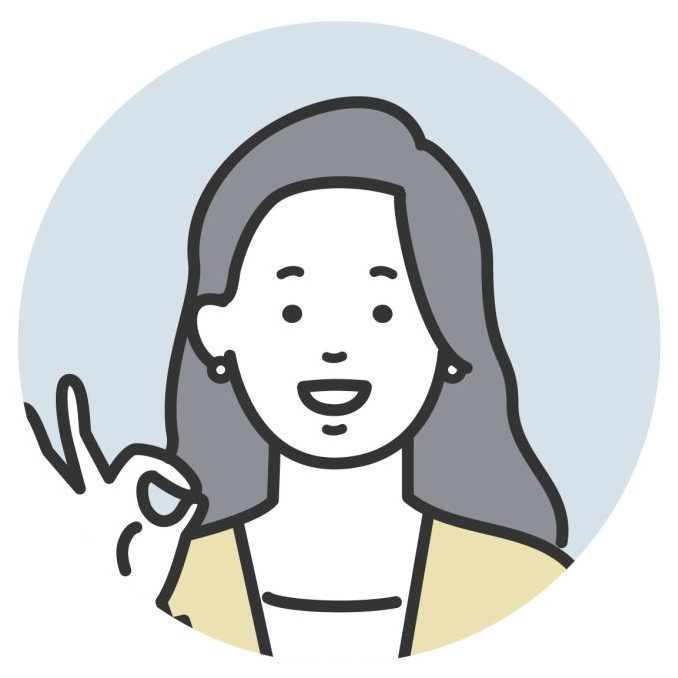
私は子供のおねしょや突然の嘔吐に備え、防水シーツを使っていますよ。
快適に眠るための寝具の選び方は、「布団が暑いと眠れないので季節に合わせて対策♪快適な寝具の選び方」も参考になりますよ。
朝起きたら窓を開け、日中は寝室のドアを開けるなどして、寝ている間に溜まったマットレスや寝室の湿気を室外に逃がしましょう。
梅雨時期など換気ができないときも、除湿器やエアコンの除湿機能をうまく活用して部屋の湿度を適切に管理できると良いですね。
高温で今いるダニを除去!エサを減らして繁殖を防ごう
ダニ対策で大切なことは、「今いるダニを除去すること」と「新たなダニの繁殖を防ぐこと」です。
マットレスを包む側生地が取り外せる場合は、シーツと一緒に高温のお湯で洗濯したり乾燥機にかけたりすることで、今いるダニは駆除できます。
- 掃除機をかける
- 天日干しや布団乾燥機で退治
- シーツからダニを落とさない
- ダニ駆除の薬剤を使う
アレルギーの原因になるチリやダニのフン、死骸は掃除機で吸い取るのが正しい方法で、布団叩きで叩くのはアレルゲンが舞うのでやめたほうが良いです。

布団専用のアダプターを使えば、家庭用掃除機の強さで吸い取れますよ。
マットレスに掃除機をかけると、ダニだけでなくダニのエサとなるフケ、アカ、皮膚片も吸い取れるので繁殖を抑えるためにも効果的です。

早速マットレスに掃除機をかけたら、予想以上にゴミが取れたので効果大です!
床にもこまめに掃除機をかけ、目に見えないハウスダウストやホコリを吸い取ることで清潔な部屋を保ちましょう。
マットレスの側生地が取り外せない場合は、布団乾燥機を使うことで生きて布の繊維に強力に張り付いているダニも退治できます。

高温の処理が可能か、マットレスの表示を確認してくださいね。
- 部屋の電気を消して1時間程度待つ
- 暗い所を好むダニが布団の表面に出できてからかける
清潔な寝具を保つためにはこまめな洗濯が必要ですが、取り外す前にシーツに掃除機をかけたり、そっと外しエサをマットレスに落とさないようしたりと工夫できますよ。
本格的にダニの駆除をするには、薬剤のスプレーやダニが好む誘引剤によって引き寄せるダニ捕りシートを使う方法があります。
自然由来の成分のみで作られているので赤ちゃんやペットがいる場合でも安心して使えますが、注意書きをよく確認してから使用しましょう。
マットレスの直置きにおすすめな厚みと通気性を紹介

新たにマットレスの購入を考えている場合、直置きにおすすめのマットレスを選ぶことでお手入れの頻度が減り、カビダニの被害を受けにくいです♪
直置きするマットレスは、体を傷めずかつ、持ち運びやすい厚みのものや、通気性の良い素材を選ぶことをおすすめします。
通気性の良いマットレスを選ぶことは大切なのですが、体を休めるためのマットレスなので寝心地も重要なポイントです。
寝心地重視派は厚みのあるマットレスを選ぼう!
寝心地と毎日のお手入れの手間を考えると、8cm以上の厚みがありなるべく軽いマットレスがおすすめですよ。
床に直置きするので、ある程度の厚みがないと寝たときにマットレスが沈み腰が床につき寝心地が悪くなってしまいます。
- 底つき感があり寝心地が悪い
- 腰が下に沈み負担がかかることで腰痛や肩こりの原因になる

体重80㎏以上の場合は厚さ10cm以上あると安心です♪
直置きマットレスは定期的にお手入れをする必要があるので、重たい物だと片付けや陰干しが面倒になってしまいます。
ウレタンマットレスは軽くてお手入れしやすく、低反発がより軽いという特徴がありますが、底つき感を感じやすい場合もあるので実際に寝心地を確かめられると良いですね。
三つ折りできるタイプを選べば使わないときは収納しやすいですし、Z型にすると自立可能で簡単に湿気対策ができますよ。
通気性の良さで選ぶ!ファイバー素材は湿気知らず
マットレスの下に除湿シートを敷く場合でも、より通気性の良い素材のマットレスを選べばカビやダニの心配が減りますよね。
特にフローリングは畳よりも通気性が悪く吸湿もしてくれないため、マットレスと床の間に湿気が溜まったままになりやすいです。
| マットレスの下 | 吸湿性 | 通気性 |
|---|---|---|
| フローリング | △ | △ |
| 畳 | ◎ | △ |
| 除湿シート | ◎ | △ |
| すのこ | ○ | ○ |
通気性の良さに着目してマットレスを選ぶ場合は、素材の特徴を理解しましょう。
| 素材 | 通気性 | 特徴 |
|---|---|---|
| ファイバー | ◎ | 空気がスムーズに流れる構造で水洗いが可能 |
| コイル | ○ | コイル部分は通気性があるが、マットレス上下の表面部の素材に左右される |
| ウレタン | △ | 小さな穴を開ける表面加工により通気性を高めることはできる |
通気性だけを求めるならファイバー素材がおすすめですが、寝心地があまり良くないという声もあります。
空気が通りやすいメッシュ生地のカバーや、防ダニ加工をしているマットレスもあるので、素材だけでなくマットレスの機能も比較して商品選びをしましょう。
自分にとって寝心地の良い素材を選んでマットレスを定期的にお手入れするほうが、毎日の睡眠の質が上がると思います♪
まとめ

- 除湿シートとは寝具の下に敷いて湿気を吸湿するシートのことで、マットレスや床にカビやダニが発生するのを防ぐ効果がある
- 定期的に干してシートに溜まった湿気を放湿する必要があるが、除湿シートは半永久的に使える
- 吸湿量の少ないものは安いが頻繁に干す必要があるため、自分のお手入れの頻度に合った除湿シートを選ぶと良い
- マットレスの直置きは安全性が保てたり部屋の圧迫感を減らしたりするメリットがあるが、湿気が溜まりやすくカビやダニ発生のリスクが高いので、湿気対策は必須
- 床やマットレスに発生するカビとダニは、人によってはアレルギー症状が出るなどの健康被害を引き起こすので注意する
- カビ対策は湿気を溜めないことが大切で、マットレスの置き方や寝具選びを工夫し、部屋の換気や定期的なマットレスの陰干しで清潔な環境を整える
- ダニの繁殖を防ぐには今いるダニを高温で除去することと、こまめな掃除や洗濯でエサを減らして新たなダニが増えないようにする方法がある
- 直置きするマットレスは厚みと重さと素材が比較ポイントで、8cm以上は底つき感がなく、軽い物はお手入れが楽で、通気性の良い素材は湿気を溜めない
マットレスを直置きして使うとカビやダニの発生リスクが高まりますが、除湿シートやマットレスのお手入れなど、しっかりした対策で清潔な睡眠環境が整えられると分かりました。
安全で圧迫感のない寝床作りのために除湿シートを正しく使い、寝室を今より気持ち良く過ごせる場所にしましょう♪
直置きのマットレスは夏場の寝汗だけではなく、梅雨時期、冬の結露など、一年中湿気が溜まりやすい環境にあります。
除湿シートを敷いていれば、カビやダニの発生を抑えられるので気持ちよく眠れますし、大がかりな寝具のお手入れが楽になりますよ♪
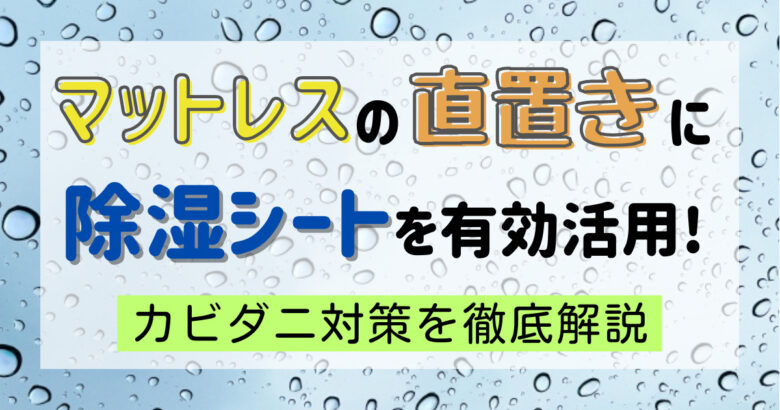

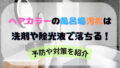
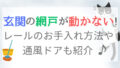
コメント